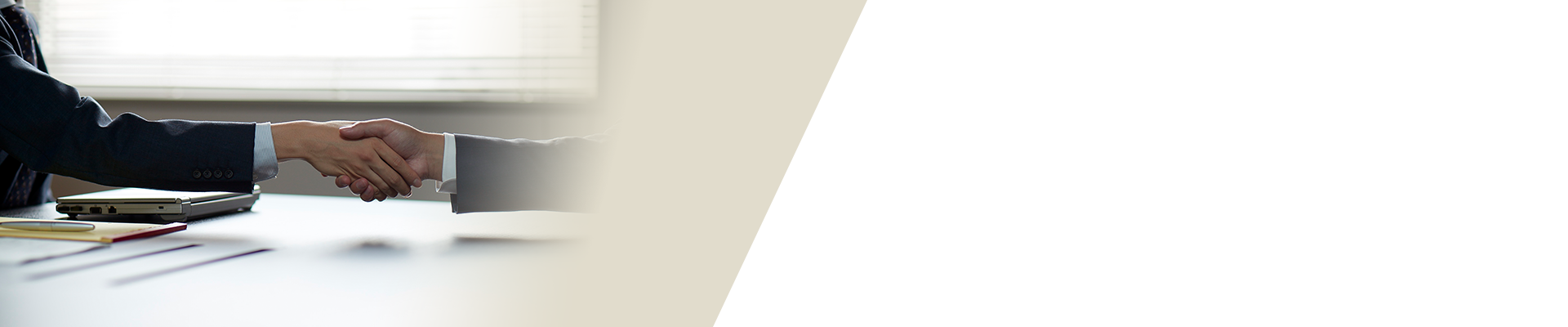
遺言・民事信託による相続対策
遺言とは何か
遺言は、被相続人(亡くなった方)が生前に、自己の財産の承継などに関して最終意思を表示したものを言います。
民法は、相続が発生した場合のルールを定めており、遺言書がない場合は、民法のルールに従って相続分の割合が決まることになります(この相続分の割合のことを「法定相続分」と言います)。これに対し、被相続人が遺言書を作成していた場合は、民法のルールよりも遺言書の内容が優先されるため、法定相続分とは異なる割合で財産を承継させることが可能となります。
例えば、父、母、長男、次男の4人家族の場合を想定しましょう。父が「長男ではなく次男に財産を全て相続させたい」と考えた場合、もし父が遺言書を作成していなければ、法定相続分に従って相続人間(母、長男、次男)で相続されることになり、次男に財産の全てを承継させることはできません。これに対し、遺言書で、「次男に全ての財産を相続させる」旨を記載しておけば、次男に財産を全て承継させることが可能となります(ただし、遺留分という制度により、相続人間で金銭的な解決が必要となる場合があります。)。
遺言書を作成した方がよい理由
死後の紛争を防ぐことができること
遺言がなければ、被相続人の死後に、相続人間で遺産分割協議を行い、各相続人の具体的相続分を決める必要があります。その過程では、遺産の範囲・評価や特別受益や寄与分などの点を巡って相続人間で意見が対立することが多いです。
これに対し、遺言により相続分や遺産分割の方法を指定しておけば、相続人は遺言書の内容に従う必要があるため、無用な紛争を防ぐことができます。特に相続人が多い場合や親族関係が複雑な場合には、意見が対立する可能性が高いため、遺言書を作成しておく必要性が高いといえます。
法定相続分と異なる割合で相続人に承継できること
上記のとおり、遺言がなければ民法のルールに従う必要がありますが、遺言がある場合は、民法のルールよりも遺言の内容が優先されるため、法定相続分とは異なる割合で財産を承継させることが可能となります。
誰にどの財産を相続させるかを決めることができること
遺言がない場合は、相続人全員の遺産分割協議により、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを決めることになります。
これに対し、遺言においては、被相続人が、特定の相続人に特定の財産を相続させる旨を定めておくことができます。
例えば、被相続人が、自分の経営する会社の後継者として長男を選定したい場合に、自社株のすべてを長男に相続させる旨を遺言で定めておくことで、円滑な事業承継を実現することができます(事業承継についてこちら【事業承継】を参照)。また、夫が妻に自宅を相続させる旨を定めておくことで、夫の死後も妻が自宅に居住し続けられるようにすることができます(なお、配偶者の保護に関しては、2018年の相続法改正により、配偶者居住権と配偶者短期居住権の制度が新設されました。配偶者居住権等についてはこちら【不動産の相続】を参照)。
相続人以外の者に財産を承継することができること
遺言がなければ、民法で定められた法定相続人のみが被相続人の財産を相続することになります。
これに対し、遺言においては、相続人以外の者に財産を承継させる旨を定めておくことができます(被相続人が遺言によって他人に自己の財産を与えることを「遺贈」といいます)。
例えば、親族ではないけどいつもお世話をしてくれている友人に財産を渡したい場合に、遺言の中でその友人に対して財産を遺贈する旨を定めておくことで、その友人に財産を承継させることができます。
遺言書の作成上の留意点
形式に不備があれば無効となること
遺言の成立要件は厳格に定められており、一定の方式が要求されます。少しでも不備があれば遺言全体が無効になる可能性があるため、民法の定める方式に従って遺言書を作成することが重要です。
民法は、遺言の方式の種類として、普通方式と特別方式を認めています。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種があり、特別方式の遺言には、死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言の4種があります。特別方式の遺言は、遺言者に死の危険が差し迫っている場合などに限定して認められる遺言で、要件面での緩和がされています。
平常時には普通方式の遺言をすることになるため、以下では普通方式のうち自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字どおり遺言者が自分で書く遺言です。すなわち、遺言者が(i)遺言書の全文、日付および氏名をすべて自分で書き、(ⅱ)遺言書に押印することにより、作成する方式の遺言です。
「自書」が要求されるため、パソコンやワープロで作成することはできません。ただし、2018年の相続法改正により、遺言書に相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録についてのみ自書することは不要になりました。例えば、不動産や預貯金の目録を作成する際に、不動産の登記事項証明書や通帳の写しを添付することが可能になりました。その場合には、添付した目録の各ページに遺言者の署名押印が必要です。
自筆証書遺言は、誰にも知られずに遺言書を作成でき、費用もそれほどかからないというメリットがある反面、方式不備で無効とされるリスクや遺言書を偽造されるリスクが大きい、遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続が必要であるなどといったデメリットもあります。なお、2018年の相続法改正に伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度を利用する場合は、偽造の危険があることや検認が必要というデメリットは解消されます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
公正証書遺言の方式要件は、以下のとおりです。
(ⅱ)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
(ⅲ)公証人が遺言者の口述を筆記すること
(ⅳ)公証人が、この筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること
(ⅴ)遺言者および証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名、押印すること
(ⅵ)公証人が、その証書は以上の(ⅰ)~(ⅴ)の手続に従って作成されたものである旨を付記して、署名、押印すること
他方で、公正証書遺言は、公証役場にて作成する必要があるため費用がかかる、遺言の内容を外部に知られる可能性があるといったデメリットもあります。
遺言能力
遺言をするには、遺言の内容を理解し、遺言の法的結果を弁識しうる能力が必要です。この能力のことを「遺言能力」といいます。
遺言能力があるか否かは、問題となる遺言の内容との関係で相対的に判断され、遺言能力がない状況で行われた遺言は無効となります。
例えば、認知症になると記憶力や認知能力が低下し、遺言の内容を理解できなくなることがあります。このような場合に遺言書を作成したとしても、のちに遺言能力がなかったとして無効になるリスクがあるため、判断能力が低下しないうちに遺言書を作成しておく必要があります。
民事信託とは何か
民事信託の内容
民事信託(「家族信託」と呼ばれることもあります)は、委託者が、受託者に財産権を移転し、一定の目的に従い、受託者が受益者のために当該財産(信託財産)を管理・処分する制度のことをいいます。分かりやすく言えば、自分の老後や認知能力低下後等に備えて、自分の自宅や預貯金等の財産を管理・処分する権限を、信頼できる家族に託すというものです。
近年、後見制度や遺言・相続制度等のほかに、高齢者の意思に沿った資産活用や資産承継の手段として、民事信託の有用性が社会に認識されつつあります。以下では民事信託を利用できる場面の一例を紹介しますが、その他にも、民事信託は様々な場面における問題解決の手法として活用することが期待されています。
民事信託を利用できる具体的な場面
老後の財産管理
例えば、本人(70歳)が、高齢で身体の衰えにより、施設への入所を余儀なくされ、自宅不動産を管理できなくなった場合の財産管理の方法として、信託制度を用いることが考えられます。
すなわち、自宅を貸家に出し、家賃収入を得る(その収入で施設料を支払う)ことを目的として、本人(委託者)が、息子(受託者)に対し、自宅不動産(信託財産)の管理・運用を委ね、その所有権を譲渡します。息子は、この信託目的に従って、自宅を貸家に出して、家賃収益を上げ、本人は、委託者兼受益者として、この家賃収益分を受け取ることができます。
親が亡くなった後の財産承継・管理の問題
例えば、本人(70歳)が、収益マンションを所有し、定期的な賃料収入があるところ、本人の死亡後は、障がいのある息子に賃料収入を受け取らせたいという場合、信託制度を用いることによりこれを実現することができます。
すなわち、本人が、受託者との間で、マンションを信託財産とする信託契約を締結します。本人の生前には本人が賃料収入を受け取る一方で、本人の死亡後には息子が定期的に賃料収入を受け取ることができるような内容で、信託契約を締結することが考えられます。このような信託によって、本人の死亡後も、間断なく財産管理を続けながら、財産の承継を図ることができます。
なお、この場合の受託者は、不動産を管理できて、かつ信頼できる親族・知人でも問題ありませんが、財産の規模等によっては、信託銀行や信託会社などの利用も検討した方がよいケースもあります。
後継ぎ遺贈型の信託
例えば、本人(X)は、後妻(Y)と自宅で居住しており、自分が死んだ後も後妻Yの存命中はYを自宅に住まわせたいと希望しているとします。しかし、Xと先妻との間に長男(A)がおり、長男Aと後妻Yの関係がよくないため、Xは自分の死後のことが不安です。
このような場合、Xが、後妻Yに自宅を相続させ、さらに後妻Yが死亡した後は、長男Aに相続させる旨の遺言をすることも考えられますが、このような遺言(「後継ぎ遺贈」と言われます。)は無効であるとする見解が有力です。
そこで、信託制度を利用することにより、Xの生前はXが受益者として自宅に住み続け、Xの死後は後妻Yが受益者として自宅に居住することが可能となり、さらに後妻Yが死亡した後は、自宅の帰属権利者を長男Aに指定することで、最終的には自宅を長男Aの所有とすることが可能となります。
事業承継の問題
例えば、本人が、会社の代表者兼所有者であり、死亡後は会社の全株式を息子に承継したいと考える場合、他に子がいれば、全株式を息子に承継すると遺留分侵害の問題が生じる可能性があります。しかし、信託制度を用いることにより、遺留分の問題を回避し、上記の事業承継を実現することが可能となります。
すなわち、株式の権利は、
②議決権を行使する権利等(共益権)
このように事業承継の場面において信託制度を用いることにより、株式の権利を自益権と共益権に分けて承継するのと実質的に同様の効果を実現することが可能となりますし、遺言や遺産分割などによる株式の承継手続が不要であるため経営に間断が生じないという利点もあるといえます。
信託制度を利用する場合は専門家に相談を
上で説明した場面以外にも、離婚や不動産管理・活用など様々な場面で信託制度を利用することが考えられ、どのような信託スキームを利用すべきか否かは、本人の目的や財産状況等によって多種多様であるため、個別具体的な事案に応じて検討することが必要です。
また、信託スキームによっては、本来享受できるはずの税務上のメリットを享受できないことも想定されるため、法律面のみならず税務面での検討も不可欠です。
このように信託制度は社会的に有用であるものの、専門的な知見が必要となりますので、ご利用を検討される際には、弁護士・税理士に相談することをお勧めします。




こんなことで悩んでいませんか?
(特別受益・寄与分) 遺言・民事信託による
相続対策 事業承継の方法と留意点 遺留分の請求をしたい・
受けた 使途不明金、遺産の調査 事実婚・
LGBTパートナーの相続対策 相続放棄とその注意点